私たちは、現実を“ありのまま”に見ていると思っている。
だが実際には、物事を直接見ているのではなく、自分の内側にある「地図」を通して世界を見ているにすぎない。
その地図とは、価値観や常識、人生経験、親からの教え、育った環境、学んだ知識など、さまざまなものが積み重なってできた“思い込み”や“前提”の集合体。
これを心理学では「スキーマ」と呼び、ビジネス書では「パラダイム」とも言われる。
地図そのものが間違っていたら、どんなに努力しても、目的地にたどり着けない。
だからこそ、自分の中にある“地図”を正確に見つめ直す力が問われている。
地図は無意識に選ばれている
ある会社の若手社員が「上司は厳しくて怖い」と感じていた。
理由を尋ねると、「質問すると嫌な顔をされた気がした」「声が低くて威圧的だ」と言う。
しかし、実際に上司に話を聞いてみると、「忙しいだけだった」「質問してくれて嬉しい」と話していた。
このように、「怖い上司」というラベルは、本人の中の地図が作り出したものだったのだ。
その地図を修正せずにコミュニケーションを取ろうとすると、ますますすれ違いが深まっていく。
私たちは、自分の地図を“真実”だと思い込むことで、知らず知らずのうちに、現実の一部しか見なくなってしまう。
これこそが、「思い込みの罠」である。
パラダイムに責任を持つということ
では、どうすれば自分の地図に気づき、より良い方向へ修正できるのか?
まず大切なのは、自分が今どんな地図を持っているかに“気づく”ことである。
自分が何に過剰に反応しているか、
何を前提として他者を判断しているか、
どんな価値観に無意識に従っているか。
たとえば、
「仕事は苦しいものであるべき」
「本音は隠すべき」
「年上には絶対服従」
といった思い込みに、あなた自身が縛られているかもしれない。
その思い込みが、日々の選択を狭めていないだろうか。
そのパラダイムが、人との関係性に影を落としていないだろうか。
自覚すれば、変えることができる。
変えられれば、現実もまた変わる。
これこそが、自分のパラダイムに対して責任を持つという姿勢だ。
他者の地図に触れると視野が広がる
もう一つ大切なのは、他者の地図に敬意を払うことである。
人はみな異なる価値観や人生経験を持ち、それぞれの「地図」を携えて生きている。
だから、行動や考え方に違いがあって当たり前。
その違いを「間違っている」と捉えるのではなく、「その人にはその人の地図がある」と理解しようとするだけで、対話の質は大きく変わる。
異なる視点に触れることは、自分の地図を磨く最高の機会でもある。
時に反発したくなる意見も、「そういう見方もあるのか」と一度受け止めてみる。
それだけで、より立体的に世界を捉えられる力が育っていく。
実例:対話で変わった関係性
私が関わったある職場では、営業部門と開発部門の間に深刻な対立があった。
営業は「開発は現場のニーズを無視している」と言い、開発は「営業は現実的でない要求ばかりだ」と不満を抱えていた。
しかし、ある日“地図を交換する”ワークショップを実施した。
互いの立場で状況を説明し、相手の苦労を聞く時間を設けた。
すると、「思っていたよりも開発は丁寧に検討してくれていた」
「営業は顧客に寄り添おうとしていた」ことがわかり、関係性が大きく変わった。
相手の地図に触れたことで、自分の地図が変わったのだ。
おわりに──完成された見方を持つために
誰しも、完全に客観的な視点を持つことはできない。
だが、主観を自覚し、他者と擦り合わせることで、より客観に近づくことはできる。
自分の中の地図を見つめ、現実と照らし合わせ、他者の意見に耳を傾け、その人のパラダイムを尊重する。
このプロセスを繰り返すことで、はるかに成熟した、立体的で豊かな世界の見方が手に入る。
それは、思い込みから自由になる力であり、他者との関係性を築き直す力でもある。
今日という一日を、自分の地図を問い直す時間にしてみてはいかがだろうか。
そこから、きっと新しい景色が見えてくるはずだ。
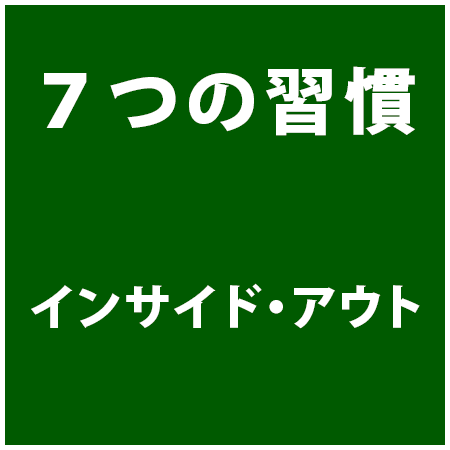

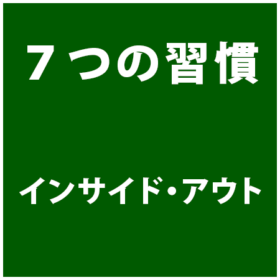
この記事へのコメントはありません。