こんな経験はないだろうか。
・子どもがミスをしたので、叱ったつもりなのに反発された
・部下にアドバイスをしたのに、まったく受け入れられなかった
・パートナーに思いを伝えたのに、ケンカになってしまった
どれも「間違ったことは言っていないはず」なのに、伝わらない。
実はここに、“正しさ”と“タイミング”のすれ違いが隠れている。
タイミングが悪いと、すべてが“否定”になる
特に、感情が高ぶっているときや、相手が傷ついているときに「正論」を投げると、それは正しさではなく、「攻撃」として受け止められる。
たとえば、子どもがテストで悪い点を取って落ち込んでいるときに、「だから言ったじゃない」「ちゃんと勉強しなきゃダメでしょ」と言ってしまう。
親としては当然の助言だと思っていても、子どもにとっては「失敗した自分を否定された」と感じてしまう。
そうなると、話の中身がどれだけ正しくても、“心の扉”は閉ざされてしまう。
本当の「教育」は、心が開かれた瞬間に生まれる
ある小学校の先生が、こんな話をしてくれた。
授業中にふざけた生徒をその場で叱ったが、全く反省の色が見られなかった。
しかし放課後、クラス全員が帰ったあとにその子を呼び、静かに話しかけてみた。
「今日、どうしてあんなことしたの?」
すると、その子はポツリと答えた。
「お母さん、今入院してて……なんか、落ち着かないんだ」
その瞬間、先生は“叱ること”の意味を深く理解したという。
子どもは「裁かれた」くない。理解されたいのだ。
そして、理解されていると感じたときにはじめて、
言葉は心に届き、“学び”として受け取られる。
関係性が先。言葉はあと。
どんなに優れた教えでも、
どんなに的確な助言でも、
関係性が壊れている状態では意味をなさない。
親子であっても、教師と生徒でも、上司と部下でも、まず大切なのは、「この人は自分を大切に思ってくれている」と相手が感じていること。
そこに信頼があれば、言葉は柔らかく届く。
信頼がなければ、言葉は刃になる。
伝えたいことがあるなら、まずは心の地ならしをすること。
そのためには、あえて“今は言わない”勇気も必要だ。
実例:家庭での「静かな対話」が生んだ変化
私自身も、かつてこんな経験があった。
息子が友達とケンカをして帰ってきたとき、怒りながら言い訳ばかりしていた。
かっとなり、「お前にも悪いところがあるだろ!」と言いかけた。
だが、ぐっと飲み込んで、夕飯まで何も言わなかった。
夜、二人だけになったとき、「今日はしんどかったな」とだけ声をかけた。
息子は泣き出し、「本当は仲直りしたいけど、どうしたらいいかわからない」と話し出した。
そのあと、自然と対話が生まれ、どう謝るか、明日どう接するかを一緒に考えることができた。
静かな時間が、対話の扉を開いた。
「伝える」は、「聴ける状態を整える」ことから始まる
伝えることの本質は、“今、相手はそれを受け取れる状態にあるか?”という問いから始まる。
どんなに良い話でも、相手が心を閉じていたら、何の意味もない。
逆に、相手が心を開いていれば、たとえ拙い言葉でも深く届く。
そのために必要なのは、
・怒りが落ち着くまで待つこと
・一対一の静かな時間をつくること
・相手の気持ちをまず受け止めること
“何を言うか”よりも、“いつ、どんな関係性で言うか”が、伝わるかどうかを決める。
おわりに──「今は言わない」という選択が未来をつくる
伝えることは、急がなくていい。
今すぐ言わなくても、明日になれば届くことがある。
今はただ、寄り添うだけで十分なこともある。
タイミングを待つことは、優しさであり、知恵でもある。
「今は言わない」を選べる人は、本当の意味で“伝える力”を持っている人だ。
今日、あなたが伝えたいことがあるなら、その前にひとつだけ自分に問いかけてみてほしい。
──「今、この人は、聴ける心の状態にあるだろうか?」
その問いから始まる対話が、きっと誰かの人生をあたたかく変えていくはずだ。
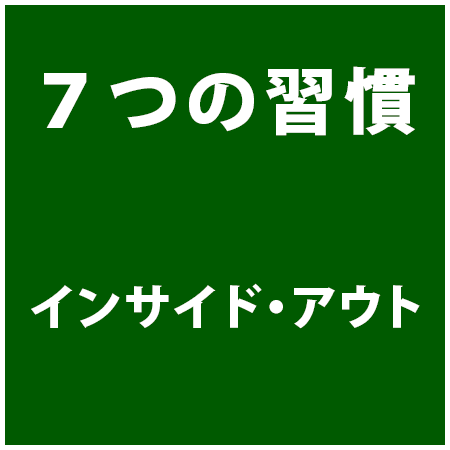

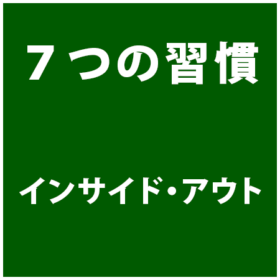
この記事へのコメントはありません。