わが子の成長を本当に願うなら、所有感を体験させ、分かち合うことの大切さを教え、そして自ら模範を示さなくてはならない。
子育てにおいて、私たち親はつい“教える側”に立とうとしてしまう。
「こうしたほうがいい」「これはやってはいけない」と、正しい道を示すことこそが愛情だと信じて疑わない。
しかし、それは本当の意味で子どもの成長を支えているのだろうか?
子どもが自分の力で立ち上がり、考え、選び、行動するには、親が“与える”こと以上に、“信じて任せる”ことが必要だ。
私自身も、子どもとの関わりの中で何度も壁にぶつかってきた。
声を荒げて後悔し、関係がぎくしゃくし、自分の未熟さに落ち込んだ日もある。
それでも、ある原則を意識し始めてから、少しずつ親としての関わり方が変わってきた。
その変化は、子どもにもしっかりと伝わっていた。
今回は、そんな私自身の体験や、実際の家庭で効果のあった実例を交えながら、**“親が変わることで、子どもも自然に変わっていく”**ための3つの視点を紹介したい。
この3つの視点を取り入れることで、子育てはより深く、豊かなものへと変化していく。
1章 なぜ“言うことを聞かない”のか?親の勘違い
「ちゃんと片付けなさい」「宿題やったの?」「ありがとうは?」
日常の中で、つい口をついて出るこの言葉たち。
どれも「正しいこと」のはずなのに、なぜか子どもは素直に応じない。
あるいはその場では従っても、翌日にはまた同じ注意を繰り返す羽目になる。
これは、親が「所有」しているつもりの子育ての失敗例だ。
子どもの行動にイライラする時、私たちは気づかないうちに“操作”しようとしている。
だが、子どもは“自分の人生の主人公”として行動したい。
コントロールされればされるほど、反発し、やらされ感に飲み込まれていく。
実際、私のクライアントでも「子どもが全然言うことを聞かないんです」と相談してくれたお母さんがいた。
彼女は非常に熱心で、良かれと思って毎日声をかけていた。
しかし、子どもに“選択の余地”がないことがすべての原因だった。
2章 「自分のものだ」と感じた瞬間、人は行動を変える
ある日、そのお母さんに「片付けなさい」ではなく、「どうしたら片付けたくなる?」と問いかけてもらった。
最初は「えっ?」と戸惑っていたが、子どもは「おもちゃの棚を決めたい」と言った。
その後はどうなったか?
子どもは、自分で決めたルールに従って、ほぼ毎日自発的に片付けるようになった。
重要なのは、“行動”ではなく“所有感”なのだ。
この所有感は、子どもが人生のハンドルを握る感覚である。
大人が握っていては、子どもはいつまでも他人の車に乗っているようなものだ。
自分の人生を自分で選び、自分で責任を持つ——この感覚を早いうちから身につけた子は、やがて思春期を迎えた時にも「自分でどうするか」を考え始める。
“やらされる”から“自分でやる”へ。このシフトが起きた時、子どもは飛躍的に成長する。
親はその土台をつくる「見えないガイド」となることを意識してほしい。
3章 親子で“分かち合う”ことが、学びの扉を開く
子どもが何か失敗した時、私たちはつい「だから言ったでしょ」と言ってしまいがちだ。
だがそれは、「あなたの失敗」と「私の正しさ」を分断する言葉だ。
私が実践していることの一つは、「共感と思い出の共有」である。
たとえば、息子が習い事でうまくいかなかった時には、私自身の“昔の失敗談”を話す。
そこで何を感じたか、どう向き合ったか、どんなことを学んだか。
すると息子は安心した表情になり、「パパもそんなだったのか」と心を開く。
この“分かち合い”こそが、親子の信頼の土台を作る。
失敗を咎めるのではなく、そこから何を得られるかを一緒に探る。
すると、子どもは“安全な場所”を手に入れ、自分で未来を切り開く勇気を持ち始める。
「失敗しても、ここに戻ってこられる」——そんな確信を子どもが持てると、外の世界で思いきり挑戦できるようになる。
それは、人生を前に進める力になる。
4章 「言葉」より「在り方」が、最も強く影響する
最後に強く伝えたいのは、親が“どんな言葉を使うか”より、“どんな在り方でいるか”が何より重要だということだ。
私たちが毎日スマホを手放せないなら、子どももそれを学ぶ。
私たちが言い訳ばかりしていれば、子どももそうなる。
私たちが「ありがとう」を大切にしていれば、自然と子どもも感謝を覚える。
あるご家庭では、「子どもに本を読ませたい」と相談を受けた。しかしその親自身、本を読んでいなかった。
そこでまず、親自身が毎日5分でも読書の時間を取るようにしたところ、2週間後には子どもが自分から「一緒に読んでいい?」と声をかけてきたという。
“模範”は、言葉ではない。
日々の姿勢、行動、表情。それがすべて、子どもに刻まれていく。
子どもにしてほしいことがあるなら、まず親がそれを実践すること。
「親が変われば、子どもも変わる」は、決して比喩ではない。
現実である。
おわりに:親である前に、まず一人の人間として
わが子の成長を本当に願うなら、コントロールすることを手放す勇気が必要だ。
「所有感を与える」「体験を分かち合う」「模範を示す」——それは、親としての役割ではあるが、同時に人間としての在り方でもある。
親であることは、学びの連続であり、成長の旅路でもある。
子どもが変わるのを待つのではなく、まず自分が変わること。
その変化が、やがて家庭全体を、そして未来の社会を変えていく。
すべては、自分から始まる。
それが“子育て”という最大の自己成長の舞台なのだ。
そして、そこには「正解」よりも、「問い続ける姿勢」が必要だ。
自分の在り方を日々問い直す親の姿こそが、子どもにとって最も深く、長く、確かな学びとなる。
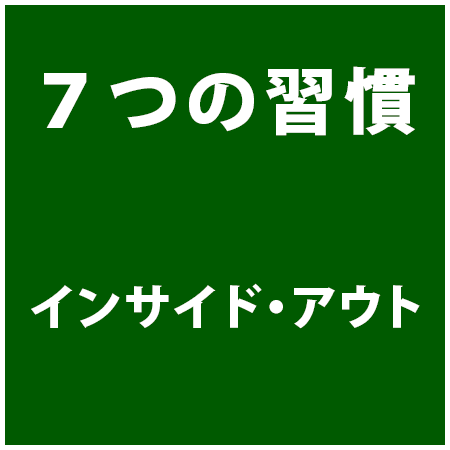

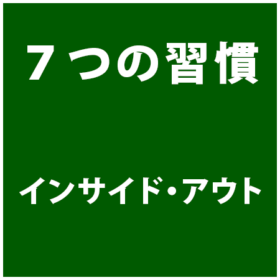
この記事へのコメントはありません。