アルベルト・アインシュタインはこう言っている。
「我々の直面する重要な問題は、その問題を作ったときに同じ思考のレベルで解決することはできない。」
この言葉には、本質的な問題解決のヒントが凝縮されている。
多くの人が、目の前のトラブルや行き詰まりを、今までと同じ視点・同じ思考でなんとかしようとする。
だがそれでは、何も変わらない。
なぜなら、今の思考こそがその問題を生み出した張本人だからだ。
今回は、視点を変えることで人生が動き出した実例と、思考の“次元上昇”を促すための実践的アプローチを紹介したい。
1章 解決できない悩みは、「視点」が同じだから
「毎日が忙しい。でも、何も進んでいない気がする」
「頑張っているのに、評価されない」
「人間関係がいつも同じところでつまずく」
こうした悩みを抱える人に共通しているのは、同じパターンを繰り返しているということだ。
同じように考え、同じように行動し、同じように傷つく。
そして、こうつぶやく。
「なぜ私ばかり、こんな目にあうんだろう」
だが、もし“問題が外にある”と考えているうちは、根本的な変化は起きない。
問題を生んだのは、自分の見方・考え方そのものかもしれないという前提に立つこと。
そこから、すべては始まる。
2章 「上の階に上がる」ように思考を進化させる
視点を変えるとは、どういうことか?
それは、今いるフロアから、階段を一段上がるようなものだ。
下の階では見えなかったものが、上の階からは見える。
同じ部屋でも、照明の当たり方が変われば、まったく違う景色に見える。
私は、ある企業のリーダー育成研修でこのアプローチを取り入れてきた。
ある中間管理職の方が、「部下が指示を聞いてくれない」と悩んでいた。
最初は「伝え方のテクニック」ばかりに意識が向いていたが、対話を重ねるうちに「自分が部下の話を聞く姿勢に欠けていた」と気づいた。
すると、驚くほどスムーズに部下との関係性が改善された。
問題は「伝え方」ではなく、「聴く力」の欠如だった。
まさに、“階を上がる”ことで、新しい視点を手に入れた例だ。
3章 視点を変える3つの問い
では、どうすれば私たちは、視点を変えることができるのか?
そのために、私は日々の中で次の3つの問いを活用している。
①「この問題の“本当の原因”は何か?」
多くの場合、目に見える問題の背後に、根本的な構造が隠れている。
表面にある“結果”だけに目を奪われるのではなく、“仕組み”に目を向けることが大切だ。
②「この状況を“もう一人の自分”が見たらどう感じるか?」
客観視は、自分の思考から一歩離れる力を養う。
感情に流されず、冷静に状況を捉えることで、自然と選択肢が増える。
③「自分が原因だったとしたら、何を変えられるか?」
問題を自分の責任と捉えることで、被害者意識から抜け出し、主体性が生まれる。
この問いは、変化を自分の手に取り戻す強力なきっかけになる。
4章 自分を変えれば、現実が変わる
以前、私の講座に参加していた40代男性がいた。
彼は転職して3社目、どこに行っても「上司と合わない」と悩んでいた。
当初は「また職場運が悪かった」と話していたが、視点を変えるセッションを通じて、「自分は指示されると反射的に反発してしまう傾向がある」と気づいた。
そこから、彼は“反応する前に一呼吸おく”という習慣を始めた。
すると、同じ上司が言っていることでも、受け取り方が変わった。
半年後、彼は「今が一番人間関係がうまくいっている」と報告してくれた。
状況が変わったのではない。彼の見方と関わり方が変わったのだ。
それによって、現実がまるで違うもののように見えてきた。
おわりに:「問題のレベル」から抜け出す力
目の前の問題をいくら叩いても、それを生んでいる“土台”が変わらなければ、何度でも同じことが起きる。
だからこそ、アインシュタインの言葉は今なお私たちに問いかけてくる。
「あなたはその問題を、どの思考のレベルで見ているのか?」
本当の変化は、視点を変えるところから始まる。
思考の階段を一段上がったとき、目の前の問題は、もはや“問題”ではなくなるかもしれない。
答えは、いつも“今の自分の外側”にある。
だからこそ、私たちは変化を恐れずに、新しい自分に出会う勇気を持ちたい。
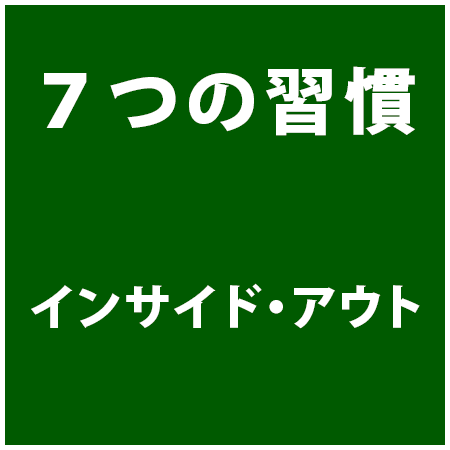

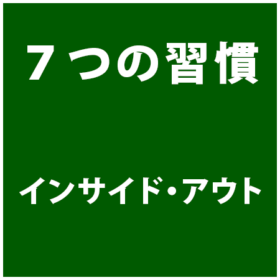
この記事へのコメントはありません。