子育てをしていると、つい「世間にどう見られるか」を気にしてしまう瞬間があります。
成績や態度、友達関係など、子どもの行動がそのまま親の評価につながると感じてしまうのです。
しかし、この視点にとらわれ続けると、子どもを本来の姿で見られなくなり、親子関係はぎこちなくなっていきます。
私自身、妻と共にそうした葛藤を経験しました。
そこから学んだのは「子どもを変えるのではなく、自分の見方を変える」ことの大切さです。
今回は、私の体験をもとに、親が世間体のレンズを外す方法についてお伝えします。
第1章 「良い親」と見られたい心理の落とし穴
親は誰しも、子どもを立派に育てたいと願います。
その願い自体は自然なものです。
しかし、「良い親だと思われたい」という欲求が強くなると、子どもを評価の道具のように扱ってしまいます。
私も妻も、息子の成績や行動を通じて「親としての社会的評価」を得ようとしていました。
学校での発言やテストの点数、友達との関係を見ては「人にどう思われるか」を気にしすぎてしまい、息子そのものを見る目が曇っていたのです。
そうした視点で見れば、息子はどうしても「不合格」という烙印を押されてしまいます。
このとき気づいたのは、私たちの視点が「純粋な親心」ではなく、「世間の目」を中心に回っていたことでした。
子どもの姿ではなく、世間にどう映るかを気にするほどに、本当に大切なものが見えなくなるのです。
第2章 ラベルを貼る危うさ
「不合格」「できが悪い」といった言葉やレッテルは、子どもの心に深く刻まれます。
短期的には「もっと頑張らなくては」と思うかもしれません。
しかし長期的には、「自分は認められない存在だ」という否定的な自己認識を育ててしまうのです。
私も息子に対して無意識にラベルを貼り、その行動を「改善すべきもの」として捉えていました。
けれども、あるとき気づいたのです。
問題は息子ではなく、彼を「不合格」と見る私たちの目のほうにあったのだと。
これは、社会の中で他人と比べられ続ける大人にも同じことが言えます。
職場や家庭で「できる・できない」というラベルを貼られると、人は本来の力を発揮できなくなります。
つまり、ラベルは相手の可能性を閉ざしてしまう危険なものなのです。
第3章 一歩離れて「本質を見る」
そこで私たち夫婦は、息子を変えようとするのをやめ、「自分たちのレンズを変える」ことを意識しました。
一歩離れて距離をおき、「彼の成績や態度」ではなく「彼の存在そのもの」に目を向けるようにしました。
彼の独自のこだわりや、人と違う考え方を否定するのではなく、「それが彼の個性かもしれない」と受けとめる努力を重ねました。
すると、彼との関係が少しずつ変化していきました。
以前は会話がすれ違いがちでしたが、彼が自分の思いを話してくれるようになり、表情にも柔らかさが戻ってきたのです。
子どもが変わったのではなく、私たちが「見る目」を変えたことによって関係が改善したのです。
第4章 実践できる3つのヒント
同じような悩みを抱える親御さんに向けて、私が実際に取り入れて効果を感じた行動のヒントを3つ紹介します。
1.比べる軸を変える
他の子どもや平均点ではなく、昨日の自分、先週の自分と比べてみる。
小さな成長を一緒に喜ぶことが大切です。
2.「評価」ではなく「観察」する
「よくできた」「できなかった」と判断する前に、「今日はこんな工夫をしていた」と客観的に観察して伝えると、子どもは安心して自己表現できます。
3.沈黙を受け入れる
子どもが話さないとき、無理に答えを引き出そうとしない。
「待つ」ことも親の大事な役割です。
沈黙を安心のサインに変えることで、やがて心が開かれていきます。
第5章 親が変わると子どもも変わる
最も大切なのは「子どもをどう変えるか」ではなく、「親がどう変わるか」です。
親が世間体や評価に縛られず、子どもを一人の人間として尊重する姿勢を持つと、不思議と子ども自身も安心し、伸びやかに成長していきます。
私たち夫婦の体験から言えるのは、子育てにおける最大の壁は「子ども」ではなく「親のものの見方」だということです。
レンズを外す勇気を持ったとき、初めて子どもは本来の価値を発揮できるのです。
結論
親が子どもを「世間の評価」というレンズ越しに見る限り、子どもは常に不足して見えてしまいます。
しかし、そのレンズを外して本質に目を向けると、子どもはありのままの価値を持つ存在であることに気づきます。
親の変化が、子どもの可能性を開くのです。
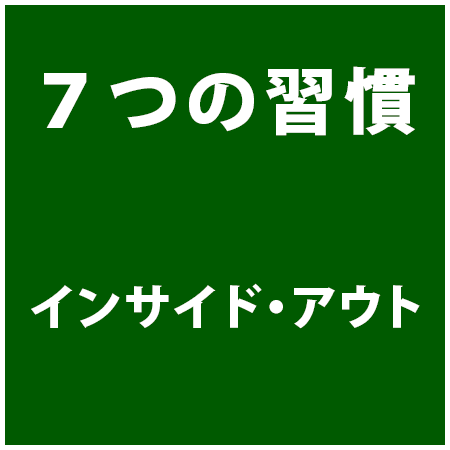

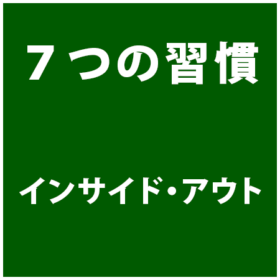
この記事へのコメントはありません。